お盆が過ぎると、信州では正直に秋風が吹いてきます。今夏は日本中が酷暑にあえぎ大変でしたが、過ぎてしまうとあのジリジリした夏の日が懐かしい。初秋は私が最も苦手な季節です。

今年は、夏の高温により稲刈りが早まりそう。そんな中、千歳屋では稲刈りに先駆けて、ホウキモロコシの収穫&乾燥作業が続いています。ホウキモロコシって何!?という方も多いことでしょう。ホウキモロコシは、タカキビの仲間でモロコシ属の一年草。背丈は2メートル以上に成長します。盛夏に穂を収穫し、座敷箒などの箒(ほうき)の材料にするのです。

我が千歳屋きって器用な(人間的には不器用)Craftsman136(クラフトマン・イサム)さんは藁(わら)工芸に取り組んでいますが、箒(ほうき)を作る会にも所属しています。箒の師匠であるノブコ先生が高齢になり、貴重な野溝箒(のみぞぼうき)の種をつないで欲しいと託されたのでした。
そもそも、種には2種類あります。1つは、昔からその地で栽培され、自家採種を積み重ねて繋がれてきた「固定種」の種。もう1つは、異なる優良な形質を持った親を掛け合わせて作られた「F1種」の種。現在の日本のお店で売っている種のほとんどはこちら、F1種です。
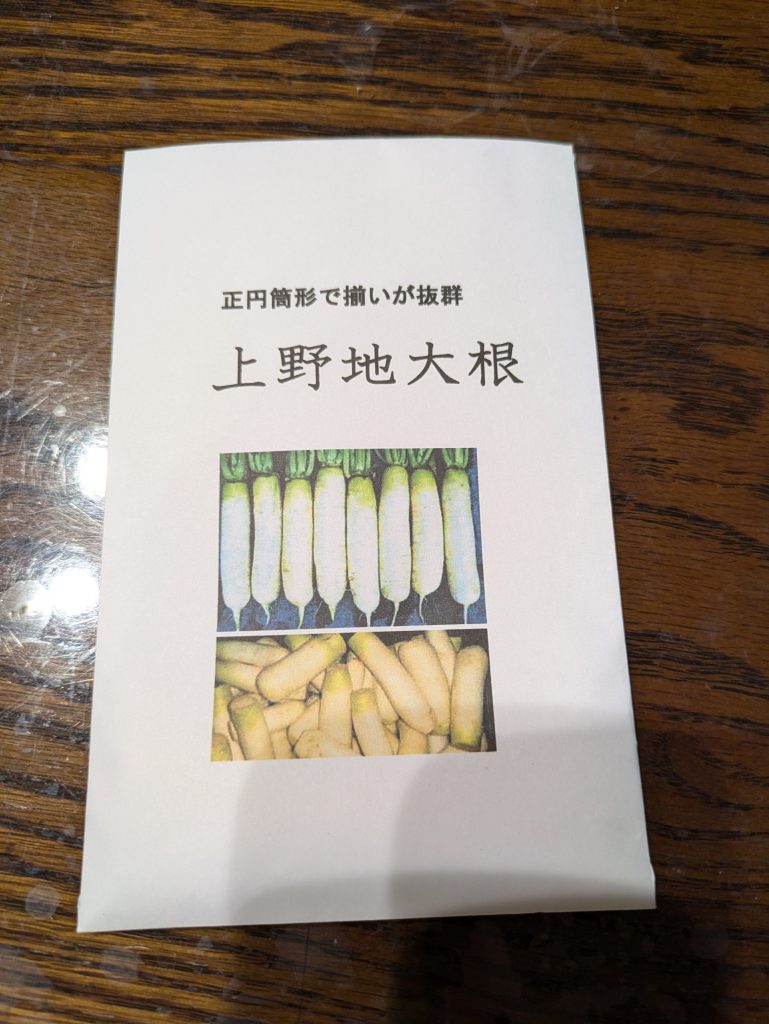
固定種「上野地大根」の種
F1種というのは「優性と劣性(品種としての優劣ではありません)の品種を交配して採種した種には、必ず優性の形質を持った種ができる」という、メンデルが発見した「優劣の法則」を利用した技術。F1種は1世代限りのハイブリッド技術、よって自家採種することはできません。
かつての私は「現代の農家は、自家採種ができないF1種を販売する種苗企業に首根っこをつかまれて、ただの栽培マシーンみたいだ」なんて偉そうに憤慨したものでした。けれどもF1種は発芽時期や生育期間が揃い、耐病性抜群。スーパーに並ぶ形の揃った野菜たち。異常気象に打ち勝ちながら、美しい工業製品のような野菜を作るにはF1種は必須です。東京オリンピックを契機とした高度成長期以降、日本中の野菜の種が固定種からF1種に置き換わったのも頷けましょう。
一方で、食と農の文化的側面を考えた時、循環型農業や有機農業を求めた時(農薬や化学肥料がない時代から栽培されてきた固定種は、その地の環境に適応して生育する力が強いため有機栽培に適していると言われます)、その地の風土に育まれた固定種は貴重な財産です。「馴化」(じゅんか)とは、植物がその地に適応し、その風土に合った子孫を残す、植物が持っ適応力のこと。馴化と交雑が野菜の歴史を作ってきたのです。
そんなわけで、我が千歳屋では固定種も大切にする農業を営んできました。稲核菜(いねこきな)、保平カブ(ほだいらかぶ)、番所キュウリ(ばんどころきゅうり)、八町キュウリ(はっちょうきゅうり)などを栽培しています🌱

長くなりましたが、かくして始まった野溝箒のホウキモロコシ栽培。延々と続く間引き、手での細やかな除草、と本当に大変。おまけに……

ギャアアア!!!!
136氏からきたラインを見た瞬間、私は思わず叫び声をあげました。なんと、前日の夕立ちで、背丈が高くなったホウキモロコシが倒伏してしまったそうな。収穫を目前に控えてのことです。
慰め、諦めること数日後、「倒れたホウキモロコシが自力で起き上がってきてる!」と136氏が言い出しました。「ノブコ先生が、紐で縛って立てておけば、じきに収穫だから大丈夫かもって言ってる」――8月の灼熱の太陽の下、昼休みに延々とホウキモロコシの救出作業をする136氏。こういう時の彼の忍耐力には脱帽です。

8月下旬、日が短くなったのを感じながらホウキモロコシを無事に収穫。余分な部分を取り除いて束ね、数日干します。


終戦から80年目の夏。命について考えることの多いこの夏に、託された種を増やすことができた喜びはひとしお。「一粒万倍」ーー1粒の種は1年後には1万倍に増え、2年後にはその1万倍で1億粒。3年後には1兆粒。種の生命力は無限で、やはり種採りは農の肝です。

